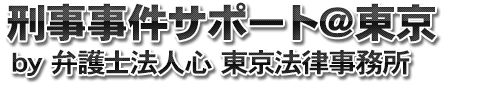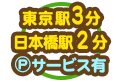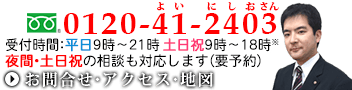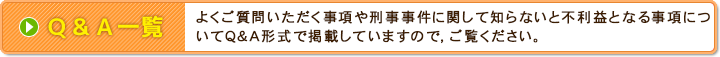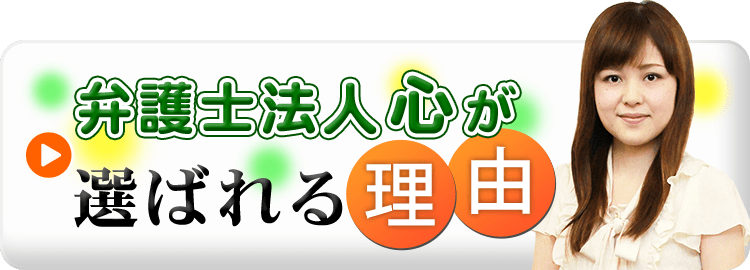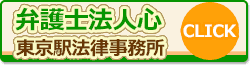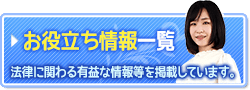「その他」のお役立ち情報
少年事件の手続きの流れ
1 処罰の目的
犯罪を犯した者は法に従って処罰されなければならないことが、法治国家の大原則であります。
なぜ罪を犯したものが処罰されなければならないのかという根本にまでさかのぼって考えると、そこには大きく二つの大きな思想的背景があることが分かります。
⑴ 応報
まず、「応報」という考え方です。
要するに、「罪を犯した者は罪の報いを受けなければならない」「人を傷つけるものは、自らも傷つけられるべきである」という考え方です。
もう少し荒い言葉でいうと「やられたら、やりかえす」という発想と言い換えてもいいかもしれません。
こう言ってしまうと非常に原始的な考え方のようにも聞こえますが、「悪いことをした人には、何か悪いことが起こるべき」という感覚は多くの人が共有する自然な感情ですし、被害者の被害感情に応えることなどを考えると、刑罰の根本に「応報」の思想はあってしかるべき考え方であると思われます。
⑵ 予防・矯正
そして、もうひとつの考え方が「予防・矯正」という考え方です。
これは、要するに「悪いことをしたら、つらい目に遭うから、悪いことはしないようにしましょう」ということを事前に周知することで、犯罪が起こるのを未然に防止しようというものです。
そして、実際に犯罪が起きた場合に刑罰を科すことで「ほら、こんなつらい思いをするんだから、二度と悪いことをするんじゃないよ」と犯罪者を教育矯正しようという考え方です。
特に、最後の「矯正」という考え方は現代の刑事司法制度を考える上で重要になってきます。
というのも、犯罪者を「矯正」しようと考えると、罪を犯した人間の犯罪の内容や、犯罪に至る経緯について詳細に検討し、「こういう状況で罪を犯した人間は、どのような手続きでどのような程度の罰を与えれば、再度罪を犯す確率を低くできるのか?」という問いに応えなければならなくなるからです。
場合によっては、刑務所に収容して自由を奪うよりも社会の中で監督を受けながら仕事をした方が、再犯の確率が高いケースもあるはずです。
2 少年事件における手続き
こういった問題意識がとりわけ鮮明になるのが、少年の刑事事件です。
現代の日本の刑事司法制度上では、少年は成人よりも家庭環境や就学・就労先の環境が良好なものに調整できた場合、再度犯罪を犯す確率を下げることができると考えられています。
これを「少年の可塑性」と呼んだりします。
そのため、少年の刑事事件は成人のものとは異なる流れをとります。
まず、逮捕・勾留されることは成人と同じですが、その後、検察官は、少年を家庭裁判所に送致し、家庭裁判所の方で観護措置をとるかを判断します。
観護措置とは、いわゆる少年鑑別所に少年を送って収容することです。
少年鑑別所は、あくまで「鑑別」を目的とした施設であり、処罰目的で収容されるわけではありません。
少年は、ここで心理テストや家庭裁判所の調査官の面接等を受けることとなります。
そして、少年鑑別所での収容期間を経て最終的に、家庭裁判所の裁判官が少年の最終的な処分を決めることとなります。
これを「少年審判」といいます。
3 少年事件のお悩みは弁護士へ
このように、少年事件は基本的な手続きの流れだけでも成人の刑事事件とは大きく異なります。
「子どもが犯罪にかかわってしまった」などという場合、どのような手続きがあるのか、将来にどんな影響が生じるのか等が気になる方もいらっしゃるかと思います。
東京で少年事件のことでお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。
刑事事件を得意とする弁護士がお悩みに対応いたします。